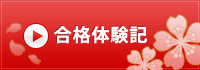現役合格おめでとう!!
2025年 新宿エルタワー校 合格体験記

東京大学
理科一類
理科一類
阿部みのり さん
( 雙葉高等学校 )
2025年 現役合格
理科一類
東進に入学したのは中3の初め頃です。高2の夏頃から、本格的に大学受験を意識した勉強を始めました。東大を目指した理由は、大学で学びたい分野が思い当たらなかったので進学先振り分け制度に魅力に感じたことと、高3の1年間を受験勉強に費やすなら最難関を目指してみようと思ったことです。
受験勉強では、ゴールを意識してやるべき事の計画を立て、それに沿って勉強を進めました。東大入試においては、全ての科目を完璧にする必要は無いので、周囲の方の客観的な意見も参考にしながら、どのような得点バランスで受かりたいかを決めることが非常に大切だと思います。私は、数学が他の科目と比較して極端に苦手だったので、数学を人並みのレベルまで伸ばそうとばかり考えていましたが、全体のバランスを踏まえ勉強時間を戦略的に配分するようにしてから、点数が安定し始めました。
受験生活の後半、特に直前期は不安な日々が続き、勉強に集中出来ない時間が増えました。自分に自信を持って最後まで努力し続けることが理想ですが、辛い時は遠慮なく周囲の人を頼ってください。私は、家族や担任の先生・担任助手の方々にたくさん助けて頂き、最後まで走りきることが出来ました。支えてくださった全ての方に感謝します。
受験勉強をしている時は、終わりが見えず、毎日勉強に向き合うことを苦しく感じることもあると思います。それでも、入試の日は必ず来るし、試験場で頼りになるのは今まで努力を重ねてきた自分自身です。最後まで自分を信じて頑張ってください。
受験勉強では、ゴールを意識してやるべき事の計画を立て、それに沿って勉強を進めました。東大入試においては、全ての科目を完璧にする必要は無いので、周囲の方の客観的な意見も参考にしながら、どのような得点バランスで受かりたいかを決めることが非常に大切だと思います。私は、数学が他の科目と比較して極端に苦手だったので、数学を人並みのレベルまで伸ばそうとばかり考えていましたが、全体のバランスを踏まえ勉強時間を戦略的に配分するようにしてから、点数が安定し始めました。
受験生活の後半、特に直前期は不安な日々が続き、勉強に集中出来ない時間が増えました。自分に自信を持って最後まで努力し続けることが理想ですが、辛い時は遠慮なく周囲の人を頼ってください。私は、家族や担任の先生・担任助手の方々にたくさん助けて頂き、最後まで走りきることが出来ました。支えてくださった全ての方に感謝します。
受験勉強をしている時は、終わりが見えず、毎日勉強に向き合うことを苦しく感じることもあると思います。それでも、入試の日は必ず来るし、試験場で頼りになるのは今まで努力を重ねてきた自分自身です。最後まで自分を信じて頑張ってください。

東京大学
理科二類
理科二類
垣花昌旦 くん
( 学習院高等科 )
2025年 現役合格
理科二類
東進に入学したのは中学2年の終わりでした。友人から「数学特待」という制度があると聞き、入学を決めました。中学生の間は数学を中心に学習を進め、高校1年生からハイレベル物理とスタンダード化学、高校2年生ではハイレベル現代文を受講し、他の教科の学習も本格的に始めました。
東進のシステムで最も良いと感じたのは「チームミーティング」です。
映像による授業では、周囲の人がどれくらい勉強しているのかが分かりにくいですが、ライバルの進捗を聞くことができるこの機会は貴重で、モチベーションの向上につながりました。数学特待では、受講講座数に制限がないため、とにかく数をこなすことに集中しました。しかし、1コマに対する予習・復習の時間を合計1時間程度しか確保しなかったため、東大模試の数学の得点は20点を超えることがほとんどありませんでした。高2の後半から、学習方針を大きく転換しました。「数学ぐんぐん基本編」から「数学の真髄東大対策」までの例題や復習問題を解き直し、授業の解説が思い浮かぶほど理解を深めるようにしました。すると、数学の得点が80点までに上昇していきました。この勉強法の転換が、大きな転機になったと思っています。
高3の学習方針について
過去問演習を多くこなすことは、学力を高めるための有効な手段ですが、僕はそれを主軸となる基本の勉強方針を決めるための材料の一つとして活用しました。過去問演習の主な目的は、時間配分、解答の順番、出題傾向 を把握することです。しかし、それだけで終わらせるのではなく、過去問を解いた結果から 自分に足りない能力を見つけ、普段の勉強に反映させること が重要です。自分の課題に応じて、適切な年数・分野を選びながら過去問演習を進めるとよいでしょう。
後輩へのアドバイス
僕の失敗談を元にアドバイスをしたいと思います。ハイレベル物理を受講する際は、次の点に注意してください。
1.理解しないまま次のコマに進まない。 疑問点があれば、すぐに校舎のスタッフに質問しましょう。理解せずに進むと、黒板を写すだけの作業になってしまいます。
2.講義ノートを丁寧に作成する。 ハイレベル物理のテキストには問題しか掲載されていないため、復習時に参照できるよう、ノートを整理して書きましょう。
3.基礎的な問題集と併用する。 ハイレベル物理のテキストは複合問題が多く、どこでつまずいているのか判断しにくいため、基礎的な問題集を解きながら進めると効果的です。
高3の人は全力で頑張ってください。
東進のシステムで最も良いと感じたのは「チームミーティング」です。
映像による授業では、周囲の人がどれくらい勉強しているのかが分かりにくいですが、ライバルの進捗を聞くことができるこの機会は貴重で、モチベーションの向上につながりました。数学特待では、受講講座数に制限がないため、とにかく数をこなすことに集中しました。しかし、1コマに対する予習・復習の時間を合計1時間程度しか確保しなかったため、東大模試の数学の得点は20点を超えることがほとんどありませんでした。高2の後半から、学習方針を大きく転換しました。「数学ぐんぐん基本編」から「数学の真髄東大対策」までの例題や復習問題を解き直し、授業の解説が思い浮かぶほど理解を深めるようにしました。すると、数学の得点が80点までに上昇していきました。この勉強法の転換が、大きな転機になったと思っています。
高3の学習方針について
過去問演習を多くこなすことは、学力を高めるための有効な手段ですが、僕はそれを主軸となる基本の勉強方針を決めるための材料の一つとして活用しました。過去問演習の主な目的は、時間配分、解答の順番、出題傾向 を把握することです。しかし、それだけで終わらせるのではなく、過去問を解いた結果から 自分に足りない能力を見つけ、普段の勉強に反映させること が重要です。自分の課題に応じて、適切な年数・分野を選びながら過去問演習を進めるとよいでしょう。
後輩へのアドバイス
僕の失敗談を元にアドバイスをしたいと思います。ハイレベル物理を受講する際は、次の点に注意してください。
1.理解しないまま次のコマに進まない。 疑問点があれば、すぐに校舎のスタッフに質問しましょう。理解せずに進むと、黒板を写すだけの作業になってしまいます。
2.講義ノートを丁寧に作成する。 ハイレベル物理のテキストには問題しか掲載されていないため、復習時に参照できるよう、ノートを整理して書きましょう。
3.基礎的な問題集と併用する。 ハイレベル物理のテキストは複合問題が多く、どこでつまずいているのか判断しにくいため、基礎的な問題集を解きながら進めると効果的です。
高3の人は全力で頑張ってください。

東京大学
文科一類
文科一類
若林一樹 くん
( 成城高等学校 )
2025年 現役合格
文科一類
【心境について】色々な方々から応援していただけたこと、そして何より今までの自分の努力を信じて入試に臨めたことが合格につながったと感じています。東大合格は、中高6年間の有終の美を飾ったという意味でも、最高学府への到達という意味でも、間違いなく18年の人生で1番嬉しい出来事でした。恵まれた境遇に感謝し、更なる研鑽を積んでゆきたいと思います。
【受験生活について】根性論を語るつもりはありませんが、受験には持久力が必須です。ここで言う持久力は心身のレジリエンスと換言してもよいでしょう。勉強や試験に真剣に取り組めば、もちろん脳にも身体にも負荷がかかります。成績が伸び悩めば多大なストレスを抱えるでしょう。当然ですが受験生といえども勉強だけでは生活が成り立ちません。冬前までは学校へ通うでしょうし、生きている限り人間関係のストレスやプレッシャーにまつわる葛藤からは逃れられません。言うまでもなく受験生は学力・体力・精神力の総合力を試されているのです。この総合力の涵養には柔軟性と自立性を兼備したマインドセットが必要です。柔軟性とはすなわち先輩・教師・担任助手の方の助言や、同じ志望校のライバルたちからの刺激を吸収する能力を、自立性とは外部から吸収した刺激を自分なりの勉強方法や心構えに昇華させ、自分なりの受験生活を構築していく能力を指します。些か抽象的になってしまいましたが、頭の片隅に入れておいてくれたら幸いです。
【東大受験について】東大入試対策には東大過去問の演習が最善の手段だと思います。優先順位を考えつつ、25年分の過去問を存分に楽しんでください。あくまで一例として書き添えておきますが、僕は「演習→復習→苦手分野の分析→勉強計画の立案及び修正」のサイクルを意識して過去問講座を利用しました。僕は高2秋C判定→共通テスト同日体験受験B判定→高3夏A判定→高3秋B判定→最終共通テスト本番レベル模試A判定→合格というルートを辿りました。判定で一喜一憂するのは構いませんが、1回A判定を逃したくらいで諦めるのは勿体無いでしょう。苦しいときこそ奮励を!
【後輩たちへ】僕の母校である成城高校では、旧帝大志望者はかなり少数であり、まして東大志望者などほんの僅かです。僕と似たように中堅高校内トップの位置にあって最難関大学を目指している皆さんは、きっと計り知れない孤独感を抱いていることでしょう。しかし決して諦めないでください。中学受験・高校受験の結果など、あなたの努力次第でいくらでも挽回することができます。東進ほど堅実に、そして愛情深く受験生活を支えてくれる場所はおそらくないと思います。可能な限り毎日登校し、戦友と切磋琢磨し、ときには担任助手の方や社員の皆様を頼りながら、皆さんが受験生活を完遂できることを祈っています。先述のとおり、多くの人にとって受験生活は総合力を試される長く苦しい戦いです。それでも高みを目指す皆さんを、心から応援しています。
【受験生活について】根性論を語るつもりはありませんが、受験には持久力が必須です。ここで言う持久力は心身のレジリエンスと換言してもよいでしょう。勉強や試験に真剣に取り組めば、もちろん脳にも身体にも負荷がかかります。成績が伸び悩めば多大なストレスを抱えるでしょう。当然ですが受験生といえども勉強だけでは生活が成り立ちません。冬前までは学校へ通うでしょうし、生きている限り人間関係のストレスやプレッシャーにまつわる葛藤からは逃れられません。言うまでもなく受験生は学力・体力・精神力の総合力を試されているのです。この総合力の涵養には柔軟性と自立性を兼備したマインドセットが必要です。柔軟性とはすなわち先輩・教師・担任助手の方の助言や、同じ志望校のライバルたちからの刺激を吸収する能力を、自立性とは外部から吸収した刺激を自分なりの勉強方法や心構えに昇華させ、自分なりの受験生活を構築していく能力を指します。些か抽象的になってしまいましたが、頭の片隅に入れておいてくれたら幸いです。
【東大受験について】東大入試対策には東大過去問の演習が最善の手段だと思います。優先順位を考えつつ、25年分の過去問を存分に楽しんでください。あくまで一例として書き添えておきますが、僕は「演習→復習→苦手分野の分析→勉強計画の立案及び修正」のサイクルを意識して過去問講座を利用しました。僕は高2秋C判定→共通テスト同日体験受験B判定→高3夏A判定→高3秋B判定→最終共通テスト本番レベル模試A判定→合格というルートを辿りました。判定で一喜一憂するのは構いませんが、1回A判定を逃したくらいで諦めるのは勿体無いでしょう。苦しいときこそ奮励を!
【後輩たちへ】僕の母校である成城高校では、旧帝大志望者はかなり少数であり、まして東大志望者などほんの僅かです。僕と似たように中堅高校内トップの位置にあって最難関大学を目指している皆さんは、きっと計り知れない孤独感を抱いていることでしょう。しかし決して諦めないでください。中学受験・高校受験の結果など、あなたの努力次第でいくらでも挽回することができます。東進ほど堅実に、そして愛情深く受験生活を支えてくれる場所はおそらくないと思います。可能な限り毎日登校し、戦友と切磋琢磨し、ときには担任助手の方や社員の皆様を頼りながら、皆さんが受験生活を完遂できることを祈っています。先述のとおり、多くの人にとって受験生活は総合力を試される長く苦しい戦いです。それでも高みを目指す皆さんを、心から応援しています。

東京大学
文科二類
文科二類
宮﨑陸 くん
( 武蔵高等学校(私立) )
2025年 現役合格
文科二類
僕が東進に入学したのは中学3年生の春です。サッカー部の活動が週5日ある中で、部活と両立しながら東京大学に合格できたのは、東進コンテンツのサポートがあったからこそです。僕の受験生活を振り返ってみると、中3と高1はあまり勉強できていませんでした。チームミーティングや担任助手の方のサポートがあり、受験勉強そのものへ当事者意識を持って関わり始めたのが、高校2年生の春ごろでした。当初は部活の疲労とモチベーションの低さからあまり集中できませんでしたが、その中でも毎日登校や高速マスター基礎力養成講座といったコンテンツを活用しながらとにかく時間を積み重ねることを意識していました。今振り返るとこの頃の時間を積み重ねようと悪戦苦闘してついた習慣が、僕の基礎力を形成してくれたような気がします。東進コンテンツの良いところは、このように隙間時間の活用のしやすさにあると思います。
高3になり、東大同日体験受験を受験したこともまた、1つの転機になりました。基礎力がついた状態で受けたことで、自分と東京大学との距離が明確に把握できたためです。そこから僕の中で受験勉強を自分で勉強方法を考え、担任の先生や担任助手の方々と相談しながらすすめるようになりました。東大対策文系数学や東大対策世界史、過去問解説授業などの良質なコンテンツを活用しつつ、部活も10月になり引退し、自分で試行錯誤する日々を続けていくうちに自身も芽生え、試験会場には比較的安定したメンタルでいけました(前日に担任助手の方々にたくさん励ましてもらいましたが)。
僕が受験期を振り返って思うのは、体力や精神がきつい時があろうと、集中できなかろうと、机に向かい、微々たる前進を続けることが何より大切だということです。量を積み重ねるのに最適な東進コンテンツを活用して合格を掴み取って下さい!応援しています。
高3になり、東大同日体験受験を受験したこともまた、1つの転機になりました。基礎力がついた状態で受けたことで、自分と東京大学との距離が明確に把握できたためです。そこから僕の中で受験勉強を自分で勉強方法を考え、担任の先生や担任助手の方々と相談しながらすすめるようになりました。東大対策文系数学や東大対策世界史、過去問解説授業などの良質なコンテンツを活用しつつ、部活も10月になり引退し、自分で試行錯誤する日々を続けていくうちに自身も芽生え、試験会場には比較的安定したメンタルでいけました(前日に担任助手の方々にたくさん励ましてもらいましたが)。
僕が受験期を振り返って思うのは、体力や精神がきつい時があろうと、集中できなかろうと、机に向かい、微々たる前進を続けることが何より大切だということです。量を積み重ねるのに最適な東進コンテンツを活用して合格を掴み取って下さい!応援しています。

東京大学
文科一類
文科一類
堀明日翔 くん
( 日比谷高等学校 )
2025年 現役合格
文科一類
僕は高2の夏に東進に入学しました。高2の冬には地歴の講座を始め、受験勉強を始めました。しかし、当時は陸上部の活動が忙しく、勉強に十分に力を入れることはできませんでした。部活動を引退するころの高3の春には、友人たちが受験勉強に集中し始める中、まだ受験勉強に時間を割けていないことに焦りが募る一方でした。そんな中、東進のチームミーティングで友人と話せたことが、良い刺激になりました。自分の実力を確認しつつ、友人と励まし合える場は、とても貴重な機会だったと感じます。
高3の夏には過去問を始めることとなりました。初めは全く点が取れず、落ち込むことが多かったですが、担任の先生や担任助手の方と計画を立てていく中で、冷静に自分に必要な勉強を見極めることができました。また、高3の夏から模試が始まりました。模試では、本番に近い形式の問題を解くことで、実践力を磨くことができました。高3の秋・冬は問題演習に集中するようになりました。この演習が、合格に大きく貢献したように思います。
僕が高校の3年間を通して、受験、更には普段の生活において重要だと感じたものがあります。それは、自信を持つことです。模試や過去問講座で思うような結果が出ずとも、簡単に落ち込むことなく、淡々とやることを追求すれば、確実に目標に近づくことができます。自信を持つためには、普段の自分の生活が、自分自身にとって信頼に値するものである必要があります。自分を信じることは簡単ではありませんが、自分の思う正しい生活を貫いてほしいと思います。
高3の夏には過去問を始めることとなりました。初めは全く点が取れず、落ち込むことが多かったですが、担任の先生や担任助手の方と計画を立てていく中で、冷静に自分に必要な勉強を見極めることができました。また、高3の夏から模試が始まりました。模試では、本番に近い形式の問題を解くことで、実践力を磨くことができました。高3の秋・冬は問題演習に集中するようになりました。この演習が、合格に大きく貢献したように思います。
僕が高校の3年間を通して、受験、更には普段の生活において重要だと感じたものがあります。それは、自信を持つことです。模試や過去問講座で思うような結果が出ずとも、簡単に落ち込むことなく、淡々とやることを追求すれば、確実に目標に近づくことができます。自信を持つためには、普段の自分の生活が、自分自身にとって信頼に値するものである必要があります。自分を信じることは簡単ではありませんが、自分の思う正しい生活を貫いてほしいと思います。